そんな疑問を持っているあなたへ。

結論から言うと、FPは資格を取らなくても勉強するだけで十分役立ちます!
この記事では、理系出身でお金の知識ゼロからFP2級・簿記2級を取得した私が、
まで、実体験をもとに解説します。
「お金のことをちゃんと学びたいけど、資格を取るのはハードルが高い…」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
目次
【結論】FPは”資格を取らなくても”勉強だけでも役立つ!
FPの知識って、”資格を取らなくても”日常生活でじゅうぶん役立ちます。
なぜなら、税金や保険、資産運用、住宅ローンなど、お金についての幅広い知識が身につくから。
たとえば、
「この保険って本当に必要?」
「老後のためにどのくらい準備しておけばいい?」
といった疑問に、自分で答えを出せるようになります。
もちろん資格取得を目指すのもアリですが、「お金の基礎知識をつける」だけでもじゅうぶん価値がありますよ。
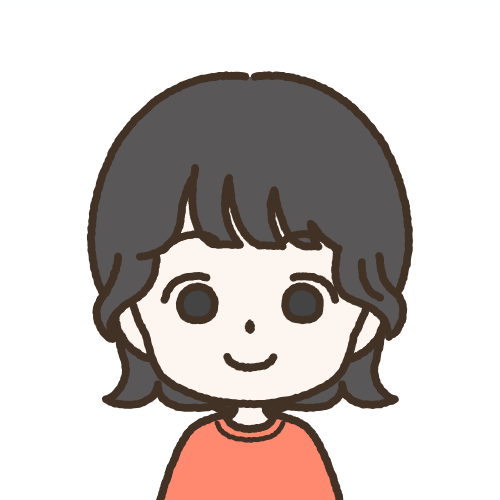
理系出身でお金の知識ゼロだった私がFP資格を目指したのは、「このレベルの知識を持っている」って自信が欲しかったから。
でも、いちばん大切なのは”学んだ知識をどう活かすか”。
FPの知識があると、経済ニュースやお金の話題にも自然と興味が湧いてきますし、積極的に関わっていくことができます。
ファイナンシャルプランナー資格ってどんな資格?
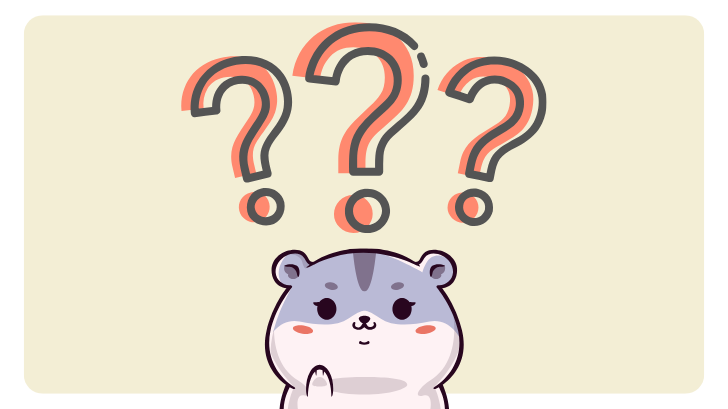
そもそも、FP資格ってどんな資格なのでしょう?
FPは、お金に関する幅広い知識を体系的に学べる資格。
税金や保険、住宅ローン、資産運用、年金、相続など、人生に欠かせないテーマを一通りカバーしています。
そんなFP資格は、大きく分けて2種類あります👇
- 国家資格の「FP技能士」(1~3級)
- 民間資格の「AFP」「CFP®」
「3級FP技能士」は入門的な位置づけの資格なので、初心者さんでも取り組みやすいですよ!

でもFP資格って、金融機関ではたらく人向けの資格じゃないの?

実際に私も理系職種で、金融関係の仕事ではありません。
私のように、「自分の家計管理に役立てたい」という理由で勉強する人も多いんですよ。
そんな人にとっては「資格を取るかどうか」より、「学んだ知識をどう使うか」が大切!
お金の基礎力がつくのは、FP資格のいちばんの魅力です。
FPで学べる”6つの分野”と”実生活での活かし方”
FP資格の勉強では、6つの分野について学びます。
それぞれ、日常生活にどう役立つのか見ていきましょう!
① ライフプランニングと資金計画
この分野では、将来必要なお金を計画的に準備する力が身につきます。
「子どもの教育費は、いつからこれ位ずつ準備しよう」
「老後資金は、いつ頃から準備できそうだな」
など、自分で考えられるようになりますよ!
② リスク管理(保険)
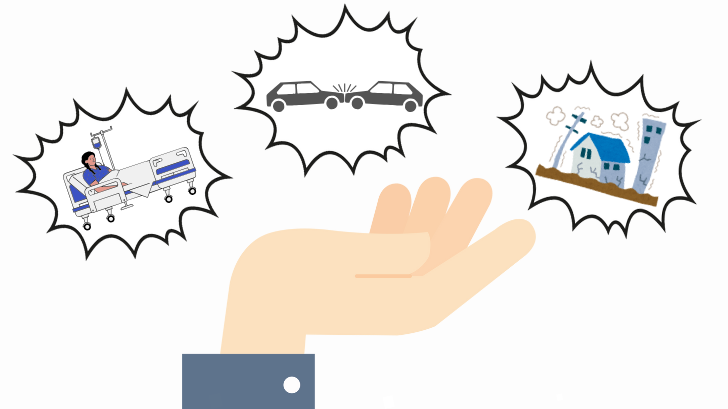
「何となく不安だから、勧められるまま保険に入っている」なんてこと、ありませんか?
この分野では、
- 定期保険や終身保険
- 医療保険
- 火災保険
といった、さまざまな保険商品の特徴を学びます。
また、「必要な保障額」の計算方法も学ぶので、本当に自分に必要な保障が判断できるようになりますよ!
ムダな保険料をカットすれば、その分を貯蓄や投資に回すこともできますね。
③ 金融資産運用

この分野では、
- 株式や投資信託などの「金融商品」
- NISAやiDeCoといった「税制優遇制度」
について、基礎から学べます。
「投資=怖いもの」と思っている方も、正しい知識があればリスクをコントロールしながら上手に資産を運用できるようになります。

なんとなくイメージがついてきましたか?
この調子で、残り3つもチェックしていきましょう!
④ タックスプランニング(税金)
この分野では、所得税や住民税の計算方法の他、
- 医療費控除や配偶者控除などの所得控除
- 住宅ローン控除
などの「税額控除」についても学習します。
会社員の場合、年末調整の書類は毎年提出しますよね。
でも、税金の仕組みはよく知らないという人も多いのではないでしょうか?

FP資格を取るまでの私は、給料明細で見るのは「手取り額」だけ…
控除項目なんて見てもいませんでした😅
損をしないためにも、税金の知識はきちんと身に着けておきたいですね。
⑤ 不動産
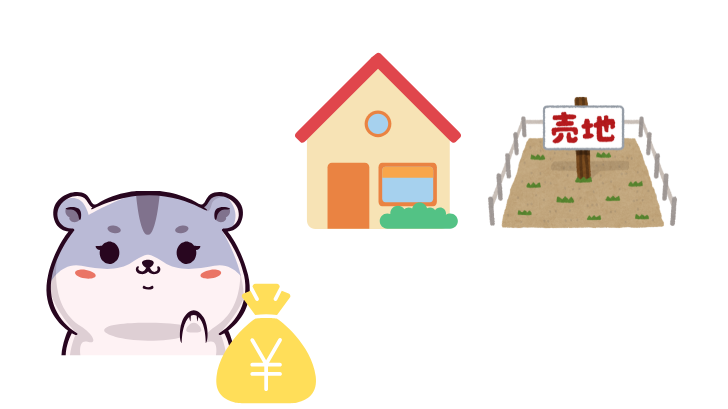
人生で最も大きな買い物といわれる住宅購入。
正しい知識を身に着けて、後悔のない選択をしたいですよね…
この分野では、
- 住宅ローンの種類や返済方法
- 頭金の目安
- 不動産にかかる税金
などを学びます。
他にも不動産の売買、賃貸に関する法律も学ぶので、「家を買うか、賃貸のままでいるか?」考えるときにも役立ちますよ。
⑥ 相続・事業承継
遺産相続の基本的なルールや相続税のしくみが理解できます。
「相続なんて、まだ先の話」と思っているかもしれませんが、将来に備えて知識をつけておいて損はありません。
この分野では、
- 法定相続人や法定相続分
- 遺言書の種類
- 相続税の計算方法
などを学習します。
相続税がかかる財産額の目安もわかるので、将来的に備えて準備が必要か判断できます。
相続税の負担を減らすこともできる生前贈与についても、知っておきたいですね。
自分が財産を残す側になったときにも、家族が困らないように準備しておきたいもの。
相続の知識は、いざというときに家族を守る力になるはずです。
資格にこだわらなくてもよい理由
あえてFP資格を取らなくても、知識さえあれば日常生活で活かすことができます。
ここでは、資格取得にこだわらなくてもいいと思う理由2つを紹介しますね。
【理由①】資格を活かす場が限られる
あなたが今、金融機関や保険会社、FP事務所などではたらいている、もしくは転職したいと思っているなら、FP資格の保有はメリットになるでしょう。
でも、そういった予定がない場合には、FP資格を取っても仕事面でのメリットはあまりないかもしれません。
【理由②】日常生活では「資格」より「実践」が大切
「自分の日常生活で活かすためにお金の知識を身につけたい」と思っているなら、必ずしも資格を取る必要はありません。
大切なのはFPの知識を実際に使い、家計の改善に役立てていくこと。
この目的であれば、まずはテキストを1冊購入し、今日から実践してみましょう!
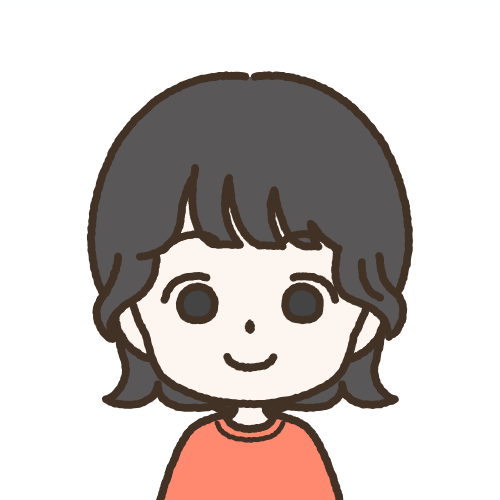
つまり、
・仕事で活かしたいならFP資格取得はメリットになる
・自分の生活に活かしたいだけなら、取っても取らなくてもOK
ってことです!
それでも資格を取るメリット!
資格取得が必須ではないとはいえ、取ることで得られるメリットもあります。
次に、どんなメリットがあるのか紹介していきますね。
【メリット1】勉強のモチベーションになる
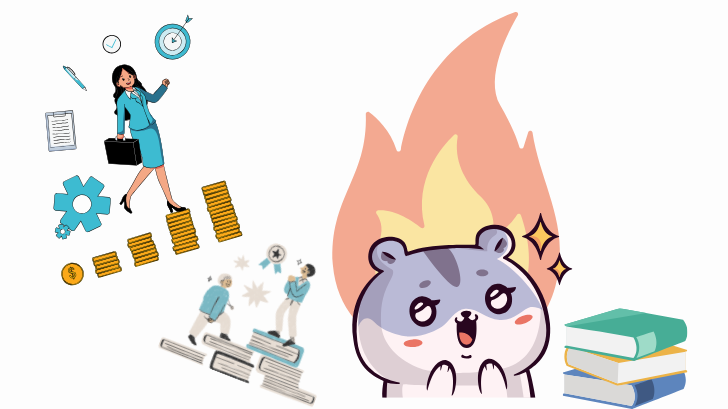
「資格試験に合格する!」という明確なゴールは、勉強のモチベーションになります。
「お金の知識を身に着ける」って漠然とした目標だけあっても、なかなかモチベーションが続かないですよね。
「○月 までにFP3級 に合格する!」という具体的な目標や判断基準があった方がやる気が出ます。
また、資格試験を受けるにも受験料がかかります。
受験料をはらうことで、「お金を払った以上、ムダにしたくない」という気持ちになりますよね。
だから、せっかく受験するならしっかり勉強しておこうという意識が生まれます。
【メリット2】知識の”お墨付き”がもらえる
資格を持っていることで、「ちゃんと理解している」ことを第三者に証明できます。
将来、金融関連の仕事に興味をもった場合にも、資格を通して自分の知識をアピールできますね
自分の努力を形として残せるのは、達成感もありますよね!
ファイナンシャルプランナーの勉強方法
FP資格の勉強方法には、大きく分けて2つあります。
自分のペースや予算に合わせて、最適な方法を選びましょう!
【勉強法1】テキストを使った独学
まず1つ目は、テキストや問題集を使った独学。
書店やネットで手に入るFP教材を使えば、費用を抑えながら自分のペースで学習できます。
特に3級レベルは分かりやすいテキストがたくさんあるので、初心者でも取り組みやすいですよ。
👇やすみんオススメのFPテキストはこちら
【勉強法2】通信講座を利用
2つ目は、通信講座を利用する方法。
動画講義やAIサポートがついている講座もあり、効率よく学べるというメリットがあります。
「独学はちょっと不安…」という方や、忙しくて勉強時間がなかなか確保できない人におすすめです。
【まとめ】学んだ知識は実践しよう!
ファイナンシャルプランナーの知識は、資格を取らなくても日常生活でじゅうぶん役立ちます。
税金や保険、資産運用など、私たちの生活に直結するお金の知識が身につくから。
資格取得は、金融関連の仕事を目指す人や、明確な目標が欲しい人にとってはメリットがあります。
でも、自分や家族の家計管理に活かすだけなら、資格の有無にこだわる必要はありません。
大切なのは、学んだ知識を実生活で使っていくこと!
「FPの勉強を始めたいけど、何から手をつければいいかわからない…」という方は、通信講座がおすすめです。
たとえば
「スタディングのFP通信講座」
など。
スマホ1つでスキマ時間に効率よく学習できますよ!

私が「保険の整理」や「家計見直し」、「投資デビュー」に踏み出せたのも、FPの勉強でお金の基礎知識を身に着けたから!
お金の不安って、「正しく知る」ことでぐっと小さくなります。
あなたも今日から、”お金に強い自分”への第一歩を踏み出しましょう!
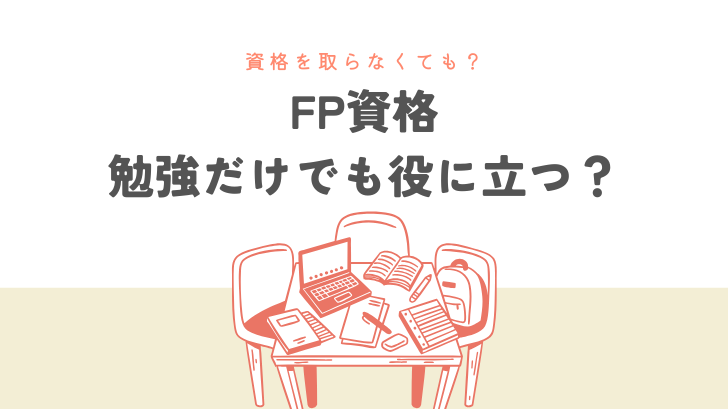
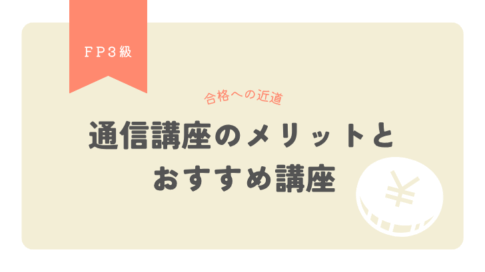
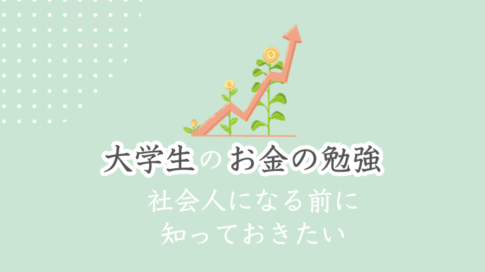
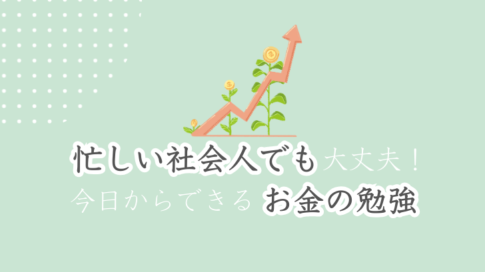
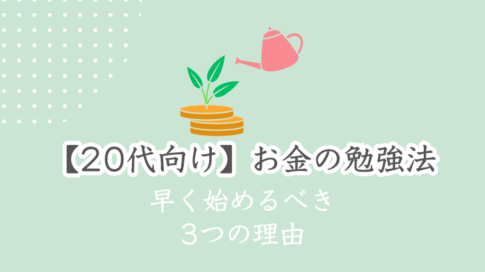
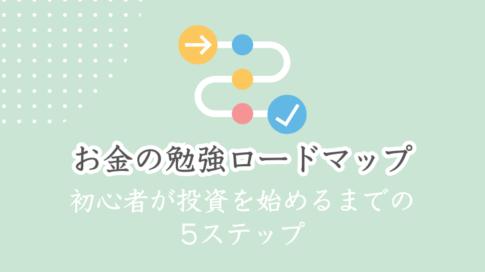

ファイナンシャルプランナーの”勉強だけ”して、資格を取らないのってアリなのかな…?